| 地図 / 国旗 | |
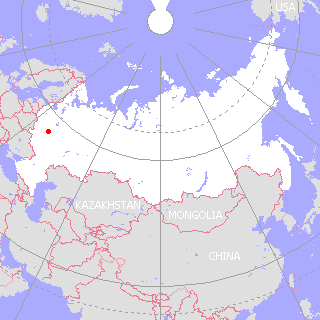
 |
|
| 国名 | |
| 日本語名 | ロシア連邦 |
| 英語名 | Russian Federation |
| コード | ISO:RU/RUS/643,NET:.ru,IOC:RUS |
| 政府 | |
| 政体 | 連邦共和制 |
| 首都 | モスクワ,Moskva(Moscow),829万7056人(1999/市内),853万7700人(1999/都市圏) |
| 独立年月日 | 1991年12月26日、ソビエト連邦解体により独立 |
| 国連加盟 | 1945年10月24日 |
| 在日公館 | ロシア連邦大使館 〒106-0041 東京都港区麻布台2丁目1-1 TEL:03-3583-4224/5982 |
| 国民 | |
| 人口 | 1億4225万7519人(2017推計) |
| 人口密度 | 8.33人/km2(2017推計) |
| 人口増加率 | -0.08%(2017推計) |
| 普通出生率 | 11.00人/1000人(2017推計) |
| 合計特殊出生率 | 1.61人(2017推計) |
| 平均寿命 | 71.0歳(2017推計) |
| 人間開発指数(HDI) | 0.804, 188ヵ国中49位(2015) |
| 民族 | ロシア人82%,タタール人4%,ウクライナ人3%,チュヴァシ人1% |
| 言語 | ロシア語(公用語),各民族語 |
| 宗教 | ロシア正教,イスラム教 |
| 地理 | |
| 面積 | 1707万5200km2(日本の45倍,米国の2倍弱,世界最大) |
| 地形 | 極東からヨーロッパにまでまたがり世界最大の面積を誇る大国。中西部をウラル山脈が南北に走り、ヨーロッパロシアとシベリアに分け、シベリアはエニセイ川とレナ川によって西、中央、東シベリアに分かれる。ヨーロッパロシアは低平な丘陵性の大平原、シベリアは西から低地、台地、山地の傾向を示す。 |
| 気候 | 北からツンドラ気候、寒帯気候、冷帯気候、温帯ステップ気と変化するが、一般に寒冷で東に進むほど年較差の大きい大陸性の特色が強くなる。ヨーロッパ・ロシアの南部は温和であるが、東シベリアは人間が居住する地域では世界の最寒地とされる。植生は、北からツンドラ、タイガ、混合林、プレーリー、ステップとなっている。西部では混合林、東部ではタイガの比率が高い。 |
| 経済 | |
| 国民総所得(GNI) | 1兆4257億0247万3026米ドル(2016) |
| 1人当たり所得(GNI/人) | 9720米ドル(2016) |
| 通貨単位 | ルーブル,Russian Rubles(RUB) |
| 為替レート | 1米ドル = 56.9167ルーブル(2018/03/05) |
| 産業 | 世界最大の国土を抱え、熱帯性を除くあらゆる農産物を生産する。特に穀物生産量が多い。しかし厳しい気候の影響もあって生産が不安定で、輸入に依存することもある。農場の多くは今も国営農場や集団農場で、民営化のペースは遅い。食肉供給が不足していたこともあり、水産物の消費量は多い。大西洋、北極海、太平洋のいずれでも大規模な漁業がおこなわれ、漁獲量は世界有数である。 地下資源は極めて豊富で、鉱物、化石燃料、宝石を産し、主要な輸出品である。特に石油と天然ガスは戦略的な輸出物資であり、政府がコントロールしている。 工業はソ連時代の計画経済により、重化学工業と軍需産業を中心に急速に発展した。しかし民生用のハイテク産業や消費財産業等は先進工業諸国に較べ遅れている。 ソ連時代は、計画経済、国営企業、集団農場などにより急速に発展、アメリカと肩を並べるまでになった。ところが80年代に入ると、豊富な天然資源と高い教育水準がありながら、官僚主義の弊害、民生技術の低下、勤労意欲の低下、軍事費の重圧などにより経済は破綻した。市場経済体制への移行を進めたが、ショック療法を伴う急進的な改革は難航し、地下経済の膨張などにより貧富の格差を広げた。さらに98年には金融不安からルーブルが大きく下落し、海外からの投資は低迷、世界経済にも大きな打撃を与えた。その後原油価格や資源価格が上昇したことで、貿易収支が改善、経済成長もプラスに転じた。 |